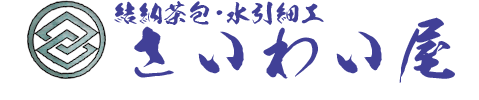水引の由来
水引の由来は飛鳥時代に遡ります。遣隋使の小野妹子が帰朝した際、同行した隋からの使者が携えていた送り物に紅白に染められた麻紐が結ばれていました。
以来、宮廷への献上品には紅白の麻紐を結ぶ習慣が生まれ、その後和紙が発明されると室町時代に麻紐から紙縒り(こより)に置き換わっていったとされています。
「水引」とはその紙縒りの事で、和紙をより合わせてそれに水糊をひいて固めて作ることからその名が付いたといわれています。
やがて時代とともに庶民の生活の中にも贈答品に水引をかける習慣が定着しました。
水引には3つの意味があるといわれています。
1つ目は開封されていないという未開封を保証する意味
2つ目は魔よけの意味
3つ目は紐を引いて結ぶということから転じて人と人を結びつけるという意味です。